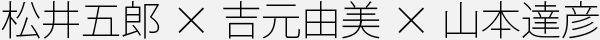FRCA-1163 ¥2,723(税込)
2006.6.21
■全10曲収録



山本:音楽が詩を邪魔することなく、かつ単なるBGMでもない、そのバランスが難しかった。音楽的には、ボサノヴァやタンゴなどをデジタル感覚に処理して、ミクスチャー的な意味ではLoungeに近い部分もあって、新しさと泥臭さを持った音。
キィワードとしては“レトロフューチャー”という音楽や考え方。それはちょうど僕も自分の音楽活動で模索していながら、まだ具体化できていないことだったんです。だから、“レトロフューチャー”へ向かいながら、それがポエトリーミュージックである、この2つが、「LG」のサウンドやメロディ制作にあたって、チャレンジでもあり、モチベーションにもなっていました。
―詩を書く上ではいかがでしたか?
吉元:今まで歌うアーティストのために歌詞を書くことが多かったけれど、この「LG」は、どのアーティストでもないところに存在する作品でしょ。そのことが、まず私にとって自由でしたね。それから、達彦さんと私はもう15年以上にわたって仕事させていただいていて、達彦さんの音楽の世界観を自分の中でわかっているつもりなんです。「Jupiter」や杏里に書く作品というのは、精神的に前向きなことを書いた作品が多くて、もちろんそれもいいと思うけれど、達彦さんの持っている世界は少し毒が混ざっていて、それは私がとても好きな世界なんですね。だから、「こんな毒っぽいところを書きたかったのよね」って、それが自分のクリエイティビティを刺激して、「何を書いてもいい」という感覚がすごく楽しかった。
山本:三人というネットワークでそれぞれが感じたことを伝達し合い、それが見事に音楽に反映されていく。これは、このプロジェクトの中で初めて経験した試みでしたね。それぞれの道でキャリアを積んだ人たちが、あえて段取りがない中で創る楽しさがあった。いつもと違う進行で客観的な意見を聞いたり、そうしたコミュニケーションの中で、作品を創っていくのは心地よかったですよ。
そうして音楽を書き終わった時点で、僕の仕事は終わりだったんです。まさか、僕がリーディングをするとは思っていなかったので。(笑)
―では、その朗読者のキャスティングについて。
松井:企画段階では、前回が声優、今回は男女一人ずつの俳優に読んでもらうことも考えていたんです。ただ、企画色が濃くなることもあり、更に、“ポエトリーミュージック”というジャンルを深く理解してもらうのは難しくて、なかなか相応しい俳優に出逢えずにいました。
僕は達彦さんが持っている雰囲気が好きで、作品でイメージしていた男性の声が、達彦さんの声に近かったんです。ただ、朗読は歌とは違います。芝居で台詞を話したり、演技をするのと同じだから、オファーを受けていただけるか心配していたんです。実際に朗読してもらったら、僕の想像以上にいいものに仕上がりました。大人の雰囲気を演出したかったこの作品を見事に表現していただいて、とてもいいキャスティンができたと思います。それから、これはすべてを録り終えてから思ったことですが、もし俳優さんにお願いしていたら「もう少し早く」や「ここまででフレーズを終わらせたい」という音楽的な資質、リズムやグルーヴ感をどこまで理解してもらえただろうと思います。
その意味でも、やはり音楽家の達彦さんに読んでいただいたことがよかったと思います。
―女性の朗読者については?
松井:彼女もボーカリストということで、“ポエトリーミュージック”に適したキャスティングだったと思います。まだデビュー前なので迷いもしましたが、今回のDemo段階で協力してもらった時の声がいい感じだったので、採用ということに。達彦さん同様、思わぬ展開ということです。
―達彦さんをご存知の吉元さんにとって、この朗読を聴いたとき、どう感じました?
吉元:それが、歌や会話をしている時と同じような感覚で自然に聴けたんですよね。
松井:そうですか。僕がお芝居や朗読の舞台を観て気になるのは、役者や読み手が過剰に表現してしまうことなんです。「BPV」で参加してくれた声優の方たちも、はじめはどうしてもキャラクターを創りこんだ声になってしまうので、レコーディングではそうならないことを心掛けていました。だから、達彦さんにも、普段話している声、その延長にある感じを大切にしていただいたんですが、それがまさに作品に命を与えた感じがします。
山本:以前、ラジオ番組のナレーションやラジオドラマで演じたことがあって、ラップではない朗読にとても興味はあったんですが、スタジオに入るまでは「マズいことを引き受けちゃったかな」(笑)と思ったりもしました。でも、実際にスタジオに入ってヘッドフォンをすると、脳が覚醒して、その世界に入り込める静けさを感じたんですよね。歌との大きな違いは、音程が無く、ことばの数が多いことですが、何よりこの作品はインプロヴィゼーション(即興)であること。先の音楽を潜在的に意識しながら、心臓と脳が瞬時に緩急を感じて、身体がそれに反応してリーディングする。歌は音程という肉体表現で、それ自体に酔ってしまうことがあるけれど、そういったことよりも、まるで抽象画と具象画を同時に書いているんだ!という感覚でした。
たとえば「黄色くうずくまる」や「僕は生まれつきの詩人だから 君のことを愛せないのだ」なんて、これはメロディという制約の中では歌えない詩なのかもしれないし、無理やりメロディにのせようと思うと、おかしくて「勘弁してよ」と思うけど(笑)、これはポエトリーミュージックだから表現できる詩なんですよ。まさに詩が自由に泳いでいる感じがしましたよね。新しいインプロヴィゼーションの世界を、今演じているということが、ものすごく楽しくなって興奮していましたね。それは、自分の書いた楽曲ということもあったし、さらに表現されている詩―ことばーを好きになっていたからでしょうね。「青の変容」や「パリに彷徨う」、そういうことばを自分で表現したいと思えたんです。
松井:日頃、僕ら作詞家は作品に「わかりやすさ」を求められることも多いですよね。クライアントにとっては、聴くひとが瞬間にメロディやことばを理解することが大切ですから。でもポエトリーミュージックのような作品では、その「わかりやすさ」にこだわる必要はないですよね。
吉元:アルバムを全部聴いてみて、すごく気持ちよかったですね。広い部屋で大きな音を出して聴くというより、i-podみたいに閉じこもって聴けるもので、そのままどこかへ深く入り込んでいきたいと思いました。
それから、いつも思うことですけど、松井さんの詩―ことばーは、私よりもずっと女性らしいし、女性のことがわかっているなって。私は女ですけど、女性のことをよくわかっていないところがある。だからといって男性がわかっているのでもないですけど、女性として私にない部分を、松井さんは持っていて「ああ、女ってそうなんだ」って気付いてしまった。(笑)
松井:最近は性別の差はどんどんなくなっていますよね。僕の中にある女性も、吉元さんの中にある男性も、一概に“女らしさ”や“男らしさ”と言えるものではなくなっているのかもしれない。今回吉元さんが男性、僕が女性の詩を書くというアプローチにしたのも、僕が男性の詩を書いてしまうと、“男の言い分”になってしまう気がしたんです。逆に、異性が書いて朗読をすることで、デフォルメの仕方がおもしろくなると思ったし、自由に書いていただいた分、二人の作家の全く違うカラーが演出できた。吉元さんの詩の方がドライですよね。場所や固有名詞が具体的で、映画のシークエンスのようです。それに対して、僕の詩は、内生のシーンやモノローグで画が止まっている感じ。その静と動を、パズルのように組み合わせた感じが、詩だけでも表現できたと思います。
山本:この朗読は新しい挑戦でしたけど、歌を歌い続けているのと同じように、僕はこの表現行為が好きで、どこか憧れがあって、日常会話であり得ないことを表現してみたいと思えたんですよ。そんな今まで使っていない脳を使うことで、新しい自分に出逢いたいという願望なのかもしれない。生涯未完成な自分を楽しんでいる人間でありたいですよね。
Libido game1 | 2 | 詩-ことば-